#1 LOST MY SENSE Ⅰ
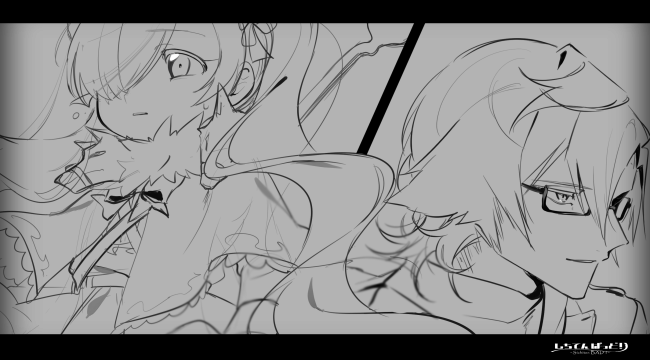
嫉妬が消えた。
その事に最初に気づいたのは憤怒だった。今朝のことだ。いつも通り、定刻になっても食卓に揃わない怠惰と嫉妬を起こそうと部屋の前で怒鳴る彼だったが、嫉妬の部屋がどうにも静かすぎる。不審に思い、ノックの後ドアノブを捻った先は、既にもぬけの殻だった。記憶には散らかっていた室内も、奇妙なほどに整然としている。立つ鳥跡を濁さず、か。などとつまらないことを口走る憤怒を押しのけ部屋に侵入した傲慢は、机の上に置かれた一枚の紙切れに手を伸ばした。彼女が昨日見ていた新聞の切り抜きだった。
面白さに波があることで有名な、紙面の片隅で連載されている風刺漫画。その結末のコマで蛇が鷲に捕らえられていたのを、傲慢は今でもよく覚えている。
何の前触れもなく、彼女は行方を晦ました。昨日までは朝寝坊して、昼食の嫌いなピーマンは残し、休憩中の傲慢にはベタベタと付き纏い、仕事の途中には道草する。そうして普段と変わらず、七顚屋内で自由奔放に振舞っていたはずだった。それが、今日の朝には雲隠れというわけだ。昨晩最後に彼女を見たのは強欲らしいが、心当たりはないと言う。一番遅くまで起きていた憤怒も、その時刻以降見かけてはいない。未明に去ったと考えるのが妥当だろう。
「色欲、位置情報は」
「これは……この部屋からですね」
色欲は手元のノートパソコンで嫉妬に預けていた携帯の位置情報を割り出そうと試みたが、反応は彼女の部屋からだった。強欲がナイトテーブルの引き出しを開ければすぐに端末が見つかった。傲慢は少し思案した後、今日に受けていた案件を先方に頼み込んで全て先送りにしてもらえないか電話をかけて交渉する。仕事の内容上、依頼そのものを断らなければならないものもあった。それでも嫉妬の捜索を最優先にすべきだと、これまでの違和感を演算した末、自身の勘が告げる。苦渋の決断だったが、反対する者はいなかった。
そんなこんなで時刻は午後四時、すっかり肌寒くなった今の季節ではもう日も落ち始める頃合。玄関前の階段に腰をかけていた傲慢は、数分前にかけた招集で先に戻っていた憤怒と暴食、強欲、そして今しがた戻ってきた色欲を確認するとゆっくり立ち上がる。
「見つかって……はなさそうだな。手がかりも無しか?」
七顚屋前に集まったメンバーを見渡す。怠惰のみ姿が見えなかったが、彼の行動が一足遅れがちなのは誰もが知る事実であるため、ここでは然程気にせずに話を進める。
「思い当たる場所を全て捜索し、聞き込み調査も行いましたが、そのような少女は見ていないと」
「どういうつもりだあの蛇女、この忙しい時期によくも手を煩わせるようなことを……」
「あにさま。わるいのがしっとさんだって決めつけてはかわいそうだわ。もしかしたら、何かわるいことにまきこまれているのかも……」
暴食が憤怒のコートの裾をつかむ。憤怒は不安げに見上げる彼女の頭をそっと撫でてやった。当然、これが嫉妬の思いつきでとられた行動ではないであろうことは、彼自身もよく理解している。いくら悪戯好きで自由人の彼女とて、組織の一員である自覚を持っているのならば仲間に迷惑をかけるようなことはしまい。ただ、原因がわかっていない今、この状況の責任を事件の当事者である彼女に押しつけでもしなければ苛立ちが収まらなかった。
「あっ、来たぞ! あれ怠惰だ!」
強欲が指さす方に視線が集まる。小走りで枕を抱えやってくる少年の影がそこにはあった。土埃ですっかり汚れてしまった外履きのスリッパが、ぺたぺたと気の抜けた音を立てながらこちらに近づいてくる。
「ごめん……っ、遅くなっちゃって……」
「良かった良かった、怠惰までいなくなったらどうしようかと思ったよ。どうだ、お前は何か掴めたか?」
久々の激しい運動に息を切らせた少年は、かがみ込んで呼吸を整える。顔を覗き込み様子を窺う暴食に大丈夫、と返して顔を上げた。
「僕、帰りになんとなくシロツメ堂を覗いてきたんだ。そしたら誰もいなくって」
「誰もいない……営業時間外だったのか? まだそんな時間じゃないだろ」
「それが、玄関のプレートは営業中のままなんだよ。変だなと思って、中に入って呼んでみたんだけど、店主さんもゆうちゃんもいないみたいなんだ」
不可解だ、と傲慢は思う。そもそも、シロツメ堂の店主は獣人の色が強く出た派手な外見から外出を好まない。加えてユウリも、仕事以外では極力外出を控えるように言われているのだと怠惰は本人の口から聞いたことがあった。店を開けたままという不注意も彼ららしくない。
嫉妬個人とシロツメ堂に深い関わりも共通点も見出せないため、安直に両者の失踪を関連性づけることは難しい。とはいえ、妙な出来事がこうも続けば不信感は拭えない。嫌な予感が加速する。
「シロツメ堂のことはわかった。で、肝心の嫉妬についてはどうだったんだ」
思い出したようにはっと怠惰が背筋を伸ばす。
「大きな黒いリボンの女の子を、朝にあっちで見かけたって人がいたよ」
「それを先に言わんか」
現在時刻からは随分前になるが、唯一の目撃情報だ。傲慢は方針を変えると、もう一度捜索場所を振り分け直し、指示を出す。各々は再び散り散りに街へと繰り出した。
そして一時間後の召集。あろう事か、憤怒と暴食はそこに現れなかった。
集合予定の時刻から少し遡り、日も完全に落ちた頃。憤怒は暴食の手を繋ぎ、路地を歩いていた。元々人通りの少ない道だったが、夜になると完全に人の気配はない。一通り見て回ったものの、侵入可能な建物も聞き込みができそうな人間も存在しない。繋いだ暴食の手も冷えている。彼女の間食用の携帯食も残り僅かだったので、少し早いがもと来た道を引き返そうとしたその時、硬い足音が闇の中に響いた。
前方に人影。警戒しながら二人はそれを見やる。憤怒はそのすらりとしたシルエットに見覚えがあった。
「……貴様は」
互いに隣り合う街灯と街灯の下に立ち、その姿を確と視認した。隻腕と言うべきか片翼と言うべきか。孔雀の翼を広げるその青年は、紛れもなく彼がよく知るシロツメ堂の店主である。ただ一つ、いつもと違う点があるとすれば、彼が見覚えのないペストマスクを装着しているということ。
「ああ。誰かと思えば、鳳仙花と橙のお嬢さん」
“鳳仙花”に”橙”とは、シロツメの店主が勝手につけた憤怒と暴食のあだ名だ。彼は顧客に花の名前をつけて管理する趣味があり、それは七顚屋に対しても例外ではない。理由は問いただしても教えてはくれなかったが、以前怠惰からユウリは花が好きなのだと聞いてから一人納得したことを思い出す。やや呆れながら憤怒は呼びかけに応えた。
「間怠い名で呼ぶなと言っているだろう。貴様、店を開けたままこんな所で何をしている、うちの怠惰が心配していたぞ」
懇意にしている仕事相手に穏やかに忠告をしながらも、憤怒は警戒を解くことができなかった。クク、と笑いながら青年は手にしていたペストマスクを撫でる。革製と思われるそれが月明かりに照らされ、不気味な艶を見せていた。表情は仮面の下。憤怒は暴食の前に手を出し、庇うように後ろに下がらせる。
「いや、ちょっとばかし急ぎの用があってね。あんまり慌てたものだから戸締りをすっかり忘れてしまっていたみたいだ……あんた達ならわかるだろう? 俺たちだって決して明るい世界の住人じゃない。”そういう”ことだってあるのさ。――さて、ここらで蛇に振り回された哀れな君たちにひとつ教えておいてあげようじゃないか」
深々とお辞儀をする店主を見て、憤怒は眉間に皺を寄せた。
店主が顔を上げる。
「俺の名は『虚飾』。己が名と引き換えに大罪を背負った罪代が一人だ」
「……待て、大罪だと? 馬鹿な。大罪は七つ、ならば罪を与えられた者も七人しか――いや、まさか」
「そうだ、あんた達は一つ大きな勘違いをしている。あの男――原罪が、俺たちに与えたのは七つの大罪などではなかったのさ。『八つの枢要罪』、勤勉な君なら覚えがあるだろう」
予想外の単語に憤怒は息を飲んだ。
八つの枢要罪。それは、暴食、色欲、強欲、憂鬱、憤怒、虚飾、傲慢の八つの悪徳の総称だ。七つの大罪の原型となった、より古い概念と伝えられる。そして憤怒は気づく、そこに嫉妬の名はないことを。これが何を意味するのかを理解した憤怒がとるべき行動は、仲間への報告。
虚飾は続ける。
「蛇と鷲はとうとう動き出した。俺にも、もう時間の猶予がない。傲慢を殺して、俺は全部終わらせる……と言えばあんた達は邪魔をするに決まっている。その前に、失せてもらおうか!」
言葉の終わりと同時に虚飾が地面を蹴る。反射的に憤怒は暴食を後ろに突き飛ばし、目の前で繰り出された回し蹴りを受け止めた。
「走れお嬢!」
「でも、あにさまが」
「行け!」
地面に尻餅をついた暴食は、立ち上がる間も目の前の彼の背から目を離すことができなかったが、意を決したように目を瞑ると振り返るなり駆け出した。その足音を確認するなり憤怒は相手を蹴り飛ばして間合いをとり、懐から出した銃を構える。
「蛇女の裏切りは理解した。しかし、貴様が傲慢を狙う理由のみが不透明だ。理由を話せ!」
対峙する仮面から返答はない。此処で奴を止め、何としても先の発言について問い詰める必要がある。
憤怒は先程蹴りを食らわされた脚に狙いを定め、引き金を引く。標的は空へと跳び、撃ち込んだ弾丸はあえなく外れた。鋭い拳銃の音が響いたころには虚飾は頭上を舞っている。速い。
「遅いな」
瞬時に踵落としが繰りだされる。加速する革靴のヒールを既の所で躱し、続けて銃口を向ける。二発、三発。静寂に包まれた夜道に乾いた銃声が鳴っても、誰も現われもしなければ通報もしない。マキア自治区は、そういう街だ。
「……チッ」
舌打ちが聞こえる。今度も避けられたものと思ったが、どうやら虚飾の翼に一発が当たったと見える。しかし、彼の動きを封じるためにはあの脚を使い物にならないようにする必要があるだろう。接近戦は恐らく不利。憤怒はなるべく距離をとろうと試みるが、間髪入れずに虚飾は飛び込んでくる。無言の蹴りを、身を低くしてやり過ごすと、そのまま手にしたコンバットナイフで相手の懐へと飛び込み左手を突き出した、が。
「なッ」
「甘く見られたものだな」
確かに虚飾の背に刃は刺さったものの、次の瞬間、憤怒はあろう事か襟を片手で捕まれた。細い体からは想像もつかないその力が、勢いと共に体を持ち上げる。空を舞う憤怒の頭の片隅に、傲慢との手合わせの記憶が過ぎった。刀で手が塞がっている傲慢が稀にやる背負い投げと似ている。コンマ数秒の思考。視界が一転したかと思えば背を地に打ち付けられた。
続けて目の前に踏み蹴りが迫る。間一髪のところで寝返り体を起こすが、二撃目の蹴りは避ける間もなく腹を重く打った。そのまま地面を転がり、建物の外壁に体をぶつける。
「くそ……」
到底、人の動きとは思えない。普段見てきた彼の姿から窺えた印象とも、大きくかけ離れている。これが『虚飾』としての力ということなのだろう。ずっとこの爪を隠してきたのか、この孔雀は。一体何の為に。
傷を負っても依然美しい姿勢で立つ彼は、狼はもう動けないと判断したのか、攻撃を止めて代わりに口を開く。
「ところで、あんたの選択はどうやら間違っているらしいことをお伝えしておこうじゃないか」
「どういうことだ」
「一つ、敵が俺一人だと思い彼女を逃がしたこと。……二つ、あんたが俺に勝てると思っていること」
憤怒の脳裏に少女の姿がよぎる。目の前の男にばかり気をとられ失念していた。そうだ、シロツメ堂は二人。手を組んでいない筈が無い。
敵は、もう一人いる。
すぐさま立ち上がって彼女が去った方角へ足を向けるも、壁に追い詰められた憤怒の目の前を虚飾の鋭い蹴りが塞いだ。無表情の鳥の仮面が、此方を見下ろしている。
「だがあんたの敵は俺だ、そうだろう?」
「そうか。ではすぐに終わらせるしかあるまい」
体勢を立て直した憤怒は眼鏡を外した。目を見開くとみるみるうちに彼の肌は体毛に覆われ、身体は倍の大きさに膨れ上がり、骨格は狼のそれへと変貌する。熱烈峻厳の捕食者の瞳が、獲物を捉えていた。
「それじゃあ、獣狩りといこうじゃないか」
振り返ることなく駆けること数分。かなり離れた所まで逃げることができただろう、と暴食は歩みを止めた。体力も既に限界が近い。路地の片隅に背を預け、肩で息をする。
「おなかが、すいた……」
そう呟いてはっとする。今自分は何と言ったか? ここまでただ彼の、憤怒の安否のみを案じ走り続けてきた彼女の思考は、気づけば徐々に自分の本能に蝕まれつつあるらしかった。いけない。空腹を感じてはならない。気を確かに持って。「わたしはおなかすいてなんかない」憤怒に出会う前の、目に映るモノ全てを見境なく食らった自分を思い出して、吐き気がする。「わたしがわたしじゃなくなる」何かを口に入れたい。座り込む。過呼吸になる。地面に手を滑らせ、適当な草を引きちぎって口にした。「あんまり、おいしくないな」これでは腹は満たされそうにない。最後にあの醜い姿を見せたのは何年前のことだったろうか。「だれか。だれかいないのかな」少なくとも七顚屋に来てからは、憤怒や他の仲間にいつも気にかけてもらっていたために、”二匹”が目覚めたことはなかった。それに、昔はまだ幼かったから暴走もそれ程酷くなかったかもしれない。もし、もしも、今ここで、もう一度自分を見失ってしまったら、わたしは、
「……暴食、ちゃん?」
頭上から降ってきた声に、我に返って声の主を見上げる。見覚えのある顔だった。
「ゆうりさん……!」
立ち上がり、小さな手で縋り付く。やっとこれであにさまを助けられる。安堵の笑みを浮かべた後、彼女は必死に、運良く現れた知人であるユウリに事情を全て話した。
「どうか、あにさまを助けてほしいの。おねがい、いっしょにしちてんやまできて」
ユウリは一瞬、動揺したような困った表情を見せ、目を伏せた。何か逡巡したような表情を見せた後、静かに首を横に振ると、徐に、彼女はその大きな手袋から己の右手を取り出した。予想外の返答に、暴食の目が見開かれる。
「ごめんなさい、暴食ちゃん。私も、本当はこんなこと、したくないんですけど、でも……」
知り合いだからと気を許していたのが過ちだった。それに気づいたのは彼女の熊の如き手が暴食の頬に触れた時だ。背負っていた護身用のナイフに手を伸ばしたが、時既に遅し。彼女の全身から力が抜け、再びへたり込んでしまう。幼い少女の心の中を、どろどろとした黒胆汁が満たし、蝕んでいく。真新しいカンバスにペンキをぶちまけたように、希望の光は絶望に塗り替えられる。もう立ち上がることは出来なかった。
「どう、して……」
その言葉を最後に、暴食は完全に塞ぎ込んでしまった。負の感情に飲み込まれ、恐らく周りは見えていまい。こうなっては暫くの間は誰の呼びかけにも応えることはできないであろうことは、ユウリ――否、『憂鬱』自身が一番理解している。都合が良いのか悪いのか、今まで与えてきた中でもかなり程度の重い抑鬱状態に陥れられたのは、自身の罪悪感と自己嫌悪に、この少女の不安定な精神状態が重なった産物か。
「本当に、ごめんなさい。でも、あの人の為だから」
手袋を着用しなおして、大きな手でそっと彼女を抱きあげる。暗い面持ちでぶつぶつと一人懺悔の言葉を繰り返しながら、憂鬱は彼と約束したその場所へと歩き始めた。
「あいつらはいたか!」
「駄目だ! 嬢ちゃんも憤怒も、嫉妬のやつも見当たらない!」
猫に化けて屋根から屋根へと走り回っていた強欲は、颯爽と飛び降り元の姿へ戻る。どうしたものかと額に手をやる傲慢のポケットから、突如場違いなほど軽快な携帯電話の着信音が鳴り響いた。色欲からの連絡だ。
「どうした色欲!」
『怠惰くんが憤怒を発見しました! ですが……』
「……何? わかった、今行く!」
強欲ははっきりとリーダーの顔色が曇ったのを視認した。電話を切るや否や傲慢は走り出す。慌てて強欲は彼の後を追った。
「なああんちゃん! 色欲はなんて!」
「怠惰が憤怒を見つけた! ただし気を失ったまま倒れてやがる、その上暴食は一緒にいなかった! 今二人が七顚屋へ運び込んでる最中らしい!」
「あ、あの憤怒が倒れてるだ!? そんなバカな!」
動揺するのも無理はない。七顚屋きっての戦闘員、傲慢に次ぐ実力を持ち、経験も多く、誰よりも戦うことに長けたあの憤怒が何者かにやられたという。つまり、行動を共にしていた暴食は既に連れ去られたとみて間違いは無い。
七顚屋の前に出ると、丁度色欲と怠惰が憤怒を担ぎ中へ入ろうとしているのが見えた。二人は急いで彼らの元へ駆け寄り、力ない憤怒の体を抱き上げる。
「オレが運ぶ! 色欲と強欲は手当の用意! 怠惰はオレの前の扉を開けていけ!」
「了解しました」
「りょーかい!」
「うん、わかった」
玄関をくぐり各々が指示通りに散らばった。憤怒の自室へと運びながら、傲慢は腕の中の男の姿を見やる。コートは血と泥で汚れ、身体には打撲痕。何本か骨を追っている可能性は大いにある。特に目立ったのは顔面の痣だ。傲慢は、憤怒がこの頭部への打撃による脳震盪で気を失ったのだろうと推察した――実際その見立ては正しく、虚飾は狼と化した憤怒の顎に蹴りを食らわせ、止めを刺している。一方で、刃物による切り傷や、銃創といった武器による攻撃は見受けられない。相手は相当の手慣れと見える。
ベッドへ寝かせ、二人がかりで衣服を脱がせる。救急箱や氷嚢を抱えた色欲と強欲が現れ、怪我の確認と手当が行われた。
「やだ、これ骨折れてるわよ。すぐに治るような怪我じゃないわ」
「こんなに痛々しい憤怒さん、僕見たことないよ……」
一通りの施術が終わり、暫し沈黙が流れる。非常に気まずい雰囲気だった。皆が苦虫をかみ潰したような顔をしている。二人の行方不明者、一人の重傷者。七顚屋に何者かの魔の手が迫っていることを、その場の全員が悟っていた。
そんな静寂を打ち破り、再び着信音。出どころはまた傲慢のポケットからだ。急ぎ携帯を取り出し、ボタンをプッシュすると耳に押し当てる。
「誰だ」
『七顚屋だな? こちらシロツメだ』
「ああシロツメか。なんか店開けてるみたいだが、お前んとこのユウリは無事か? こっちは朝から嫉妬は失踪するわ、今憤怒がボロボロで帰ってきて暴食が連れ去られてるわで大変なんだ。用があるなら後に」
『実はその件で電話を寄こしたんだ。今からいう場所に来てくれると嬉しいんだが』
傲慢は色欲に筆記具を出すように伝える。虚飾が告げた住所を復唱し、彼女にメモをとらせた。覚えがある。一度とある仕事で調査したことのある曰く付きの物件だ。
「今からそこに向かえばいいんだな?」
『ああそうだ。くれぐれも気を付けてこい』
そうして傲慢が耳元から携帯を離そうとした時だった。
「……今、なんて」
微かに、小さな声で、『にいさん』と。彼の耳にはそう聞こえた。その言葉を反芻する。暫く画面を見つめていたが、首を振り何も無かったことにしてすっくと立ち上がる。
「怠惰はここに残って憤怒を見ていてくれ。オレと色欲、強欲で今からあいつの所へ行く」
既に支度を済ませた様子の色欲と強欲は立ち上がり、傲慢と共に部屋を出ていった。
「怠惰ぁ、あんちゃんの事、頼んだぞ。あいつは無理にでも動こうとするだろけど、そんな状態じゃ来られても足手纏いだ。起きても眠らせちまえ」
「わかったよ。ごーよくくんたちも気をつけて」
怠惰は部屋の入り口から出ていった三人にそっと手を振り見送った。皆が行ってしまったのを確認すると、ベッドの傍に置かれた椅子に腰掛ける。そしてベッドの上に横たわる彼の姿を心配げに見やった、のだが。
「……お嬢、は」
「う、うそ……もう、起きたの……」
そこにはさっきまで目を覚ますことのなかった憤怒が、体を起こそうとする姿があった。